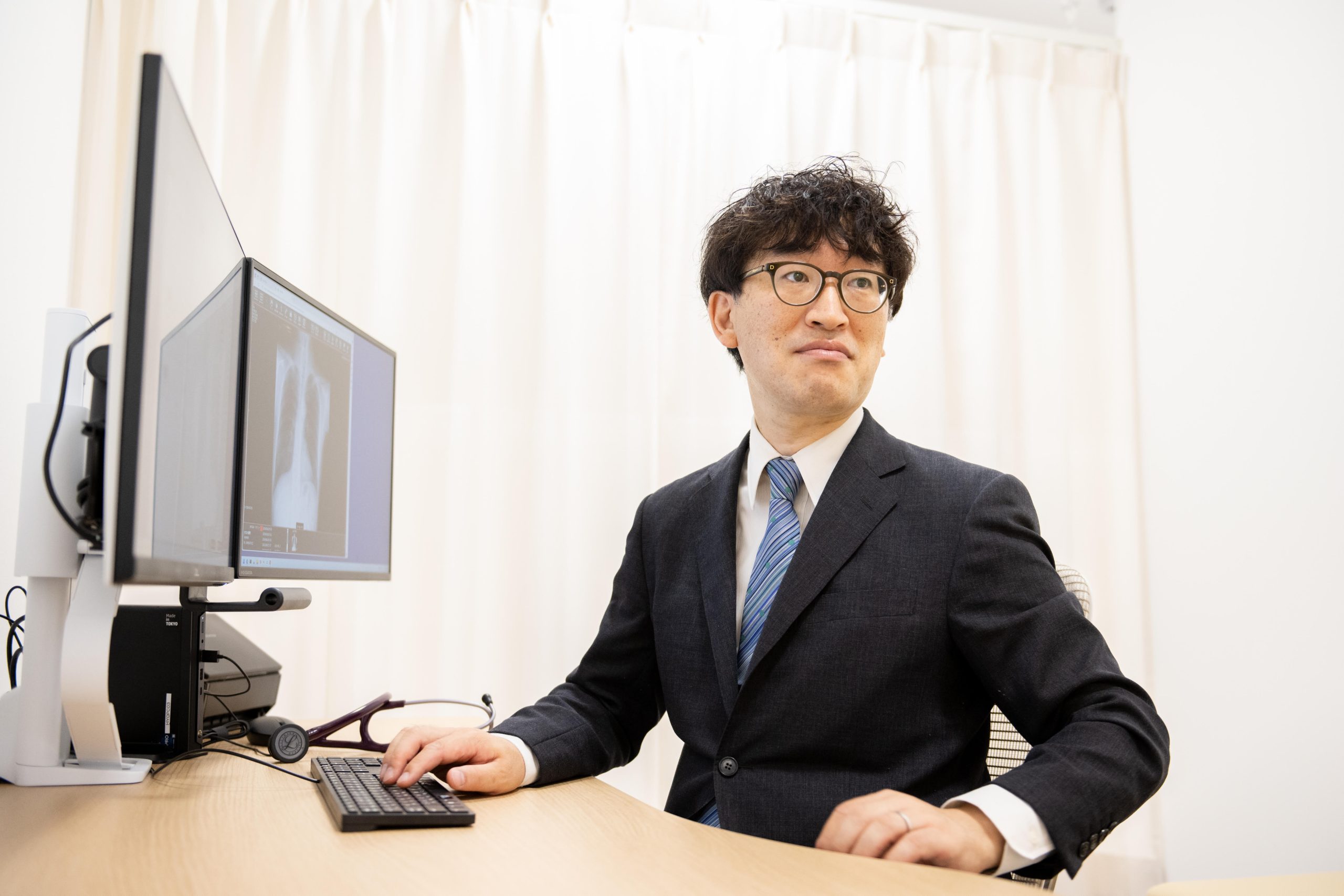
日吉いわさ内科・循環器内科 院長 岩佐 健史
「患者の言葉に耳を傾けよ。患者はあなたに診断を告げている」 ウィリアム・オスラー博士
日吉いわさ内科・循環器内科
院長 岩佐 健史
略歴
_________________________
東京大学教養学部理科3類、医学部医学科卒業。日本内科学会総合内科専門医、
日本循環器学会循環器専門医、日本腫瘍循環器学会評議員・ガイドライン協力員。
卒後すぐには医局に所属せず、
国立国際医療研究センター病院 (新宿区) で多彩な先輩・仲間と共に総合診療・内科の基礎を研修した。
在学中より志していた循環器・心臓内科の道を究めるべく、
同領域のメッカとされている心臓血圧研究所付属榊原記念病院 (府中市) で専修医を務めた後、
母校の東京大学医学部附属病院に戻り博士の学位を取得。
国立がん研究センター中央病院 (東京都中央区) で腫瘍循環器領域の学会設立・ガイドライン策定等に中心的な役割を果たした後、2024年に「日吉いわさ内科・循環器内科」を設立。
_________________________
現在の仕事についた経緯
心臓の収縮力や血液・体液量、血管の性質や弾性などが力学的モデルで関連しあう複雑系という物理学的側面、日々の高血圧診療や生活習慣病管理などの慢性期診療と心筋梗塞の心臓カテーテル治療などの急性期診療の両面があるという時間的ダイナミズム、死亡確認の際に脈が止まっているのを確認することに象徴されるように生命を支える臓器の1つであるという重要性、など在学中から心臓・循環器学に魅了されており、卒業後は迷いなく循環器内科に進路を決めました。
出身大学の医学部は国内のみならず海外からも最高峰の研究者・診療家が集まる環境でしたが、純粋培養で視野が狭くなることをおそれ、卒後すぐには入局せずに国立国際医療研究センターで研修させていただきました。この際に循環器だけでなく総合診療に携わらせていただいた経験、広く日本中から集まった熱意ある先輩・同僚と過ごした経験が、総合診療+循環器での開業、という現在につながっています。
仕事へのこだわり
周囲の医師・医療従事者には、親戚が医師で継ぐべき立場・医院があったり、大病をして助かった経験があり恩返ししたい、という理由で志した方が多いのですが、私は一切そういう縁がなく、何も知らないまま医学部に進学しました。しがらみがないという意味で、フラットな視点で専門分野や所属施設を選べたというメリットもありましたが、医療業界に長く身を置けば自然に身につくはずの常識・考え方を欠いているというデメリットもあります。
スタートラインで出遅れている、という焦りもあり、医師になって最初の5年間は「病院の敷地内に居住できる」という条件で職場を選んでおり、その後も徒歩で病院にいける範囲に住むようにしていました。24時間365日いつでも呼び出される可能性があり、プライベートな時間がほとんどないですが、その分患者さんが急変した際などは、1番早く駆けつけることができます。拙い知識と技術なりに貢献することで、一歩一歩少しずつ、患者さんや職場の信頼を勝ち取ることができました。業界の慣習や常識に縛られず先入観なしに新しい知見や技術を取り入れる、常に最前線に身を置き現場に貢献する、この2つが結果的に自分の強みになっていると思います。
今後の展望・私の夢
医師になって最初の10年間は、最高峰・最先端の環境に身を置き、24時間全力で循環器診療に取り組んできましたが、専門医や博士号を取得して一段落ついたタイミングで、上司であり恩師である永井良三先生 (現・自治医科大学学長) に紹介され、国立がん研究センター中央病院に赴任しました。科長の大橋健先生 (現・国立がん研究センター中央病院副院長) らに導かれ、「Onco-cardiology (腫瘍循環器学)」という、がん治療・腫瘍学と循環器病を結ぶ架け橋となる領域・学会の設立に携わらせていただきました。
「循環器基礎疾患があるせいで十分ながん治療が受けられない」「抗がん剤や放射線治療の影響で心臓が悪くなった」という、専門分野間のエアポケットのようなところで頼れる専門家もなく苦しみ戦っている患者さんが多数いることを知り、少しでも助けとなるようガイドライン作成等に取り組ませていただきました。2024年よがん拠点病院を離れて実地医家として開業医をしておりますが、引き続き現代医学の光が届かない学際領域に手を差し伸べていきたいと考えています。
若者へのメッセージ
座右の銘として引用させていただいたウィリアム・オスラー博士の言葉で「医学はサイエンスに基づくアートである “Medicine is an Art based on Science.”」というものがあります。正しい医療を提供するには幅広く正確な知識が必要ですが、情報だけでは十分ではなく、現場で得た経験や技術も欠かせない、という意味だと理解しています。
現代社会は効率化しており、知識を収集するだけならば、インターネットやAIを駆使し、コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを追求することで、以前の何倍・何十倍の効率で学ぶことができることでしょう。しかしながら、一見無駄な回り道や、地道な努力が、やがてその人だけの “Art” として結実する、というのはなにも医療業界に限ったことではないと思います。
「若い頃の苦労は買ってでもしろ “Heavy work in youth is quiet rest in old age.”」という言葉を贈りたいと思います。
日吉いわさ内科・循環器内科
https://hiyoshi.clinic/